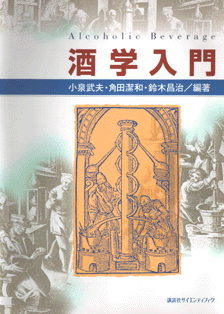Distillery Report
    
ISLAY
Bruichraddich
今回、予定外の訪問となったアイラ。ここではまだ訪問したことが無かったBruichraddichへ。いつものように、ボウモア蒸留所のクリスティンにご挨拶。今回は日本よりの団体様の対応に忙しく、あまりゆっくりとお話をする時間無かったものの、とりあえず、歓迎していただき今回は何日アイラにいるのかと。2日間で、明日はBruichraddichに行きたいので、電話番号を教えてほしいと告げると、いつものようにさっと電話してアポイントを取ってくれた次第。ゆっくりと案内できなくて申し訳ないといって、Bowmore17年のミニボトルを戴きました。こちらこそ、いつもアポイントなしで突然訪れる変なお客でごめんなさい。
さて、無事Bruichraddichへ。
この蒸留所は、5年ほど閉鎖されていたものを、近年注目株のボトラーMurray McDavidが2000年12月に買い取って再開させた。以来ラベルデザインも一新し、瓶詰めアルコール度数を43%から46%に変更し、チルフィルター処理、着色、樽同士のブレンドを廃してMMDのコンセプトをそのままオフィシャルボトルのボトリングにも適用したユニークな試みを行なっている。
個人的な見解であるが、ボトラーはウィスキービジネスの中で最もエンドユーザーに近く、マーケットの意思を最もキャッチしやすい立場にあるように思う。つまり、飲み手に近い立場から商品の選択が出来、作り手に対してはより消費者に近い立場から商品設計のアドヴァイスが可能であると言えるだろう。よって、近年のモルトウィスキー市場での消費者の嗜好に合わせた商品設計に他の作り手よりも早く開始できるに違いない。
やはりこの蒸留所では、近年のピーティーなウィスキーの市場での人気を察知し、従来の軽いピートのBruichraddichとは正反対の非常にピーティーな"PORT CHARLOTTE"の蒸留をはじめている。ニューポットをノージングさせていただいたが、非常にピーティーで蒸留精度が高く(アルコール分70%程度と言っていた)力強いものだった。従来のエレガントなアイラ、Bruichraddichとは一線を画すそのモルトには注目に値する価値がある。去年初めて蒸留を行なったのであと9年は市場に出す予定が無いと言うことであった。今から出来上がりが楽しみである。
ピーティーなウィスキーだけではない。彼らは、今ウィスキー市場で「昔ながらのつくり」のウィスキーが注目されており、それらが大きな利益をもたらしていることも見逃してはいない。再開したこの蒸留所の売りはなんと言っても「70年代の蒸留所の設備、可能な限り蒸留所設立当時(Est.1881 !!)の設備をそのまま使いウィスキーを造ること」をコンセプトととしている。
大量に生産すること、規模の拡大に主眼がおかれたウィスキービジネスに一石を投じる試みになってくれることを願う。それにしても思うのは、フロア―モルティングはそんなに効率が悪いのだろうか。そこまで昔ながらの設備を大切に使うことをコンセプトの中核に置きながらモルティングはポートエレンで行なっているそうである。ちなみに、Bruichraddichのフェノール値は10ppm、Port Charlotteは40ppmという原料モルトを指定しているそうである。単純に考えてもBruichraddich第二のモルトは「4倍くさい」と言うことになる。
さて、全体的な製造工程の話に移る。まずはミルから。これも多くの部分が木製の大変古い設備を大切にメンテナンスしながら使用しているらしい。他の蒸留所のそれに比べて確かに古い。これがどれほど、製品としてのウィスキーに影響を与えるのかは、疑問であるが、とにかく古い機械であることには違いは無い。マッシュタンはホーロー製で開放。これも古い設備だそうで見た目にもかなり年季が入っているようである。ウォッシュバック。これもオレゴンパインを使用した大変古いものを使用している。この醗酵過程はいささか他の蒸留所とは違う印象を受けた。まず、たいていの蒸留所が使用している攪拌装置が無いこと。これについて尋ねたところ、十分に大きな醗酵容器を使用した場合攪拌の必要は無いという考えらしい。また、醗酵工程に十分な時間をかけて生きた酵母が全くいない状態まで醗酵を進めることが重要であることを強調していた。これは、蒸留工程において生きた酵母がいると都合が悪いからだと言っていた。また、イーストについては通常、多くの蒸留所ではブリュワリ―イーストとディスティラリーイーストを混ぜて使うことが一般的だが、この蒸留所ではディスティラリーイーストのみを使用しているそうである。ちなみに、ウォッシュの最終アルコール度数は7%程度で醗酵温度は20度程度で温度管理は行なうことなく自然の気温に任せるがままのようである。蒸留器はウォッシュ、スピリッツ各二基づつの二組。大きさは標準的。加熱方法はスチーム。これも古い設備で、中でウォッシュスティルの下の部分はなんと、創業当時からのものだそうである。つまりスチームで加熱する以前から使われていたもの!!スチームを通すパイプは後から付けた物なのだ。スピリットセーフも一つは特有の青い錆びのついた70年代のもの。もう一つは新しくステンレス製のものである。
熟成樽については、特にこれと言ったポリシーは無いらしい。さすがオーナーがボトラーだけあってその辺はおおらかである。
フレッシュ、レフィルシェリーからバーボンは勿論、ポートやラムまで、ホッグスヘッド、バレル、パンチョン、ポートパイプ…実に多彩である。ただし、やはりシェリーカスクは高価なので多くはバーボンのようである。私的な意見では、素直な酒質のBruichladdichはシェリーもいけるし、ポートも悪くないのでは?
|
15 Feb. Islay --- Edinburgh
 フェリーでポートエレンからケンナクレイグに到着。 フェリーでポートエレンからケンナクレイグに到着。
朝8時50分にボウモアを出発。コーチ、フェリー、コーチと乗り継いで、エディンバラに到着したのは夕方6時半近く。
今回の旅で最も長い移動となった。3年ぶりのエディンバラ。何もかもが懐かしい。いつもここへ着くと迎えてくれるブリュワリ―の香りも健在だ。宿は常宿のピルリグ・ストリートのゲストハウス。重い荷物を抱えての道のりは長いものの、リーズナブルな料金と居心地の良さには変えられない。
さて、荷物を置いて早速、ソサエティーへ。リストを見ながら…やっぱり、アイラから来たのだからアイラ?いや最初はスペイあたりから…などと考えることしきり。まずはコーヒーか!!カウンターでオーダー、"Excuse me!"と声をかけたら「日本人の方ですか?」と???よく見れば確かに東洋人らしきスタッフ。よくよくお話を伺えば日本人スタッフ。僕も驚いたけど、向こうも驚いた様子。日本人のスタッフの方に会うのは初めてと告げると、彼も日本人のゲストは初めてと言う。なんだか不思議である。昨今のウィスキーブームでソサエティーの会員数は増えているはずなのに訪れるメンバーは少ないと言うことか。
とにかく、3年前とは明らかに変わったのが、旅をして日本人に出くわす事があるようになったこと。
やはり、ウィスキーはブームと言うか、メジャーになりつつあるのだろうか。
16 Feb. Edinbugh
 エディンバラのゲストハウス"Balfour House"の部屋 エディンバラのゲストハウス"Balfour House"の部屋
朝からロイヤルマイル方面へ。
いつもの事ながら、あらゆる物の調達に追われて時間が過ぎる。一日中歩き回りクタクタ。気がついてみれば夜になっていた。
週末の夜は何処も満員。一人旅を続ける者としては寂しくなる。良さそうなレストランを見つけても一人では入れない。
ア―。寂しい。という事で、グラスゴーに出かけてみる。思ったよりもすっかり様変わりして…
グローバル化したというのか、ハイカラになったと言うのか。なんだかね〜。
ところで、世界中の何処の街角にもスターバックスとマックを作るのがグローバル化なんですかね〜。
ちょっと、考えさせられる一日。しかしなんだかんだ言っても、スタバを利用してしまう自分が悲しい。
17 Feb. Visitting Crief
今日は少しばかり朝から小雨がちらほら。結構歩くかもしれないし、初めての場所なので雨は少し気が重い。乗りなれた
Scottish City Linkのバスでパースへ。パースからはローカルなバスでクリーフからは…行ってみないとわからない。
運良くエディンバラを出発してすぐに気持ちのいいスコットランド晴れ。
クリーフの町からやっぱり歩かされました、町中から。およそ20分程、一面芝生の風光明媚なところをテクテク。
看板の矢印は近そうに見えるのだけど、行った事の無い所だから余計に長く感じてしまう。道に迷っているのではないかと不安にも思うし。
今まで見せてもらった蒸留所とは一味違う、その様子。日本でいえば、観光バスが必ず立ち寄る甲府あたりのワイナリーみたい。
じじばば、カップル…観光客ばかりで一人で乗り込んだ、ウィスキースペシャリストはいささか場違いな感じ。
ともあれ無事見学を済ませ、ティスティング。ここで、£2.30払って飲ませてもらったカスクの12年とオフィシャルの18年はうまかった。詳細はディスティラリーリポートで。
さて、帰りはパースで一杯やって、という計画だったのだ、ところが、この町、日曜日のせいもあるのだろうけれどもなんだか静かで、今ひとつ。少し、キースっぽい。(キース=スペイサイドの"今は昔"的な町)
という事で、一路エディンバラへ。
結局、ローズストリートのお気に入りのパブへ二軒行って、開店したばかりのワインバーを発見しここへ。
大当たり。プロヴァンスのヴィオニエで始まって、OZのシラーズを二杯頂きながら、クルミとスティルトンのパテ オートケーキ添え、ブラックオリーブのオリジナルマリネ―ド、仕上げは本格的なカフェラテ。どれも、ワインはたっぷり、料理もコーヒーもたっぷりの量で、以上しめて日本円で3,000円と言ったところ。良心的なお店だな。私もがんばらねば…
それにしてもおかしなもので、ワインを覚えてからと言うもの週に一回はワインを飲まないと落ち着かない。でもやっぱり、ワインは一人で飲む酒じゃないな〜。
ところで、おいしいワインと料理で大満足。やたらニコニコ変な客だったんだろうな。
18 Feb. Visitting Glenkinchie
本日は、まず始めにRoyal Mile Whiskyで商談。思いのほか商売熱心なようで、比較的シッピングコストも抑えられビールのシッピングもさほどいやな顔をせずに引き受けてくれた。この分だと今後も好い取引が出来そう。
さて、商談もうまくまとまり、午後からグレンキンチ―へ。インフォメーションでも言われていたように、バスの終点からは30分弱歩かされる羽目に。毎度の事ながら、いいかげんな看板を頼りに、寂しい一本道を歩いてゆくのは意外に心細い。
ところで、ローランドの蒸留所は初の訪問。思った以上に他の地方とは違う風景に幾分、新鮮な思い。緑の美しい一面の草原が続く中にぽつんとあらわれるその蒸留所は穏やかな印象。荒波のしぶきがかかる、アイラの蒸留所や、いかにも谷間の偏狭に立つスペイの蒸留所とは雰囲気を異質なものとしている。ファームハウスが似合うのんびりとした風景。
ただ、風景がおおらかだからと言ってその酒質も短絡的に穏やかな物だと決めてはいけない。この蒸留所のモルトはローランドの中ではスモ―キーなニュアンスが強く、決して言われているほど軽くは無い。今一度、考えなくてはならないと思うのは、必ずしもローランドは軽い、とは言えないと言う事である。つまり単純にワインの産地がその特性を現すように、ウィスキーも産地がその特徴を表すかのような錯覚はそろそろ見直したほうがいいだろう。詳しいことは、Distillery Repotで。
帰りは少し雨が降り始め、今回の旅行初めての雨の中の歩き。正直、あまりいい気分ではないがこの天気の悪さも無くてはスコットランドに来た気がしない!?
エディンバラに戻る頃には雨も止んで、最終日の取ると言うことでパブクロール開始。「今日は、エールはカスクコンディションのみで、夕食はパブご飯。」をテーマにローズストリートからグラスマーケットまで飲み倒し。夕食はビーハイブインで。マッシュポテトを添えた一品を。やはり、本格的レストランを抱えるパブだけあってその味わいは素晴らしい。でも、マッシュポテト、C&Sも同じ味。自信を深める。(少し自慢)
BOW BAR。今回ジャケットを買ったブティックのスタッフに教えてもらった、エディンバラで最もトラディショナルなスコティッシュバー。確かに…さすがです。数々のカスクコンディション、さりげなく並んだモルトの数々。やはり年齢層は高め。今風の店とは全く違う、BGMも無い、昔風のいい店に久々に酔いしれた次第。こういう店はいつまでも無くならないでほしいと願わずにはいられない。
やっぱりいいね、エディンバラ。本当にいい町です。本日もご機嫌で帰宅です。
Distillery Report
   グレンタレット蒸留所周辺 グレンタレット蒸留所周辺
Southern Highland and Lowland
Glenturret and Glenkinchie
まとめて、スコットランド南部と大雑把な括りはいささか乱暴な気もするが、必要以上に地理的な細かい括りをする事に疑問を感じる私としては、とりあえずこの括りをさせていただきたい。
さて、今回の旅行では2日間に渡りGLENTURRET とGLEN KINCHIEの二つの蒸留所を訪問した。言うまでも無く、これら二つの蒸留所は南ハイランド地方、ローランド地方と分けられている。と言うことは、全くカテゴリーの異なったモルトと考えた方がいいのだろうか。いや、そもそもモルトウィスキーの生産地域はその酒質にどれほどの影響を及ぼすのであろうか。これについては以前ウィスキーマガジンの記事でも特集されていたので詳しくはそちらを参照されたい。モルトウィスキーの酒質を決定するのは、ワインと同じように考えられる宿命的な土地との繋がりよりはむしろ、何か他の要素を感じる。さて、前置きはこれくらいにして本題に移る。
始めは、グレンタレットから。
この蒸留所は、スコットランド内のみならず海外においても有名である。その理由を簡単に述べさせていただく。第一にスコットランド最古のウィスキー蒸留所として知られている。第二にこの蒸留所でねずみの捕獲に一生をささげた猫は世界一の記録を樹立し、ギネスブックに登録されている。第三に年間、最も多くのヴィジターを迎え入れていることで知られている。つまり、最もスコットランドの観光資源として重要な蒸留所と言う事も出来る。さて、以上の三点のような、特筆すべき特徴を備えた蒸留所は意外に、背後を小さなタレットリヴァーが流れ、いかにも人目を避けて立てられた、密造と言うひびきが似合うようにひっそりと佇んでいた。
見学のツアーは順調に進行する。特にこれと言った大きな違いに気づかされることはないが、多くのヴィジターを迎え入れる蒸留所にしてはこじんまりとした印象で実に好意感が持てる。最後の工程、つまり熟成と瓶詰について、少し話が他の蒸留所に比べ長かった。基本的には、バーボン・カスクとシェリー・カスクの両方を使用するとの事。ただし、熟成年数によって二種類の原酒を混合して使用すると言う。シングル・カスクのモルトが注目を集める中、オフィシャルのボトルの良さはこのような、己の蒸留所の原酒を知り尽くした人たちの手によるバランスの良さかも知れない。これは特にこの蒸留所の18年物を飲むと感じられると思う。
小さいけれど、小奇麗でしゃれた町クリーフは、時間が無いのでゆっくりとすることは出来ないが、初夏から秋にかけてスコットランドの最もいい季節にもう一度訪れてみたい。小さい田舎町ではあるが、スペイサイドに比べて、なんとなくおおらかで、過ごしやすく感じるのは気候のせいもあるのだろうか。それは、グレンタレットの酒質にも現れているような気もする。土地とウィスキーの繋がりは何を意味するのだろうか。技術的な宿命ではない何かを感じずにはいられない。
   グレンキンチー蒸留所周辺 グレンキンチー蒸留所周辺
私個人として、初めて訪問するのローランドの蒸留所はグレンキンチー。今まで何度もスコットランドを訪れているのにもかかわらず、何故かローランドの蒸留所訪問は初めてなのです。こんな言い方をしては失礼だとは思うのですが、今ひとつマイナーなイメージがぬぐえないローランド・モルト、だから、なかなか蒸留所にもたどり着けなかったのかもしれません。
さて、この蒸留所のウィスキーは通称「エディンバラ・モルト」とも呼ばれ、ローランドの蒸留所の代表格的な存在と言ってもいいかもしれません。実際には、エディンバラの市内に蒸留所があるわけではなく、少し離れた田園風景の美しい郊外に1837年に立てられたそうである。このEAST LOTHIAN地方は{スコットランドの庭園」と呼ばれており、広々とした草原が美しいのんびりとした地方である。スコットランドの首都、エディンバラの近くだけあってなんとなく洗練された田園と言った感じである。蒸留所もそんな風景の中に、その赤レンガつくりの建物を横たえている。遠くからも目に付く茶色い煙突がどのガイドブックにも載っていてこれが印象的である。
やはりUDVの主力蒸留所だけあって出来る限り近代的な設備を採用しているようである。少しお話を伺ったところ、生産するモルト原酒のうち、およそ90パーセントがブレンデッドに使用されるそうである。どのブレンデッドに何パーセント使用しているのか尋ねたところ、わからないと言う解答だった。機会があるたびに、ブレンデッドの使用原酒に付いての質問はするようにしているのだが、ほぼ100パーセント解らない、と言う返答である。これは、私の推測に過ぎないがそれぞれのブランド名を持つウィスキーは、ブランドの味覚的なコンセプトが存在し、それに合わせてブレンディングをしているだけなのではないか。つまり使用する原酒は決まっているわけではなく、手持ちの原酒の中から適切なものを選択し、使用しているのではないか。と言うことは、ブレンデッドの使用原酒を特定する、もしくは、推測することがどれほどの意味を持つのであろうか。少し、自分の質問に反省。だが、単純な興味として酒飲みのたわごと的な楽しみであることは事実か。懲りずに今後も、スコットランドで不毛な質問を繰り返してしまいそうである。
グレンキンチーからの帰り道、雲行きも怪しくなってきたので少し急ぎながら…「ん!何か変な音。雷?」と思いきや、蒸留所のすぐ近く頭上に何本もの送電線。そこから発せられている異常な音。きっとこの界隈は、不自然な磁界になっているに違いない。体に悪そう。以前聞いた話では北欧などでは強力な電磁波を発する送電線の下には保育園などを建設してはいけないそうである。そう考えると、送電線の近くの蒸留所は?どうなのであろうか。科学的には、電磁波と人体や動植物への影響の因果関係は完全には解明されていないそうで現在のところ、なんとも言えないかもしれないが。
そんなこんなで、今回の旅最後の蒸留所訪問となったグレンキンチー。怪しい雲行きの中、送電線のことを考えたり、近くから漂ってくる草の匂いや、馬糞(?)の臭いに気をとられながら早足で歩きつつ、二本の足で蒸留所を訪れる効率の悪い自分の旅の素晴らしさに気付かされた。第一に、何度もこの地に足を運ぶ言い訳が出来ること、第二に、臭いとか音とか車に乗っていたら気付かないことも肌で感じることが出来ること。そんなわけで、今後も効率の悪い旅を続けていこうと決心した帰り道。雨が降っても、寒くても、南の島への憧憬の念を抱きつつ、またこの地を訪れてしまう自分がそこにいた。「さぁ、エディンバラについたら、パブで一杯だ。」
|
19 Feb. To LONDON from EDINBURGH
 ロンドンのホテルの部屋 ロンドンのホテルの部屋
初の試みでスコットランドを周ってからロンドンに入るというコース。逆の場合に比べ、イングランドとスコットランドの違いを如実に感じる。田舎と都会の差と言ってもいいのかもしれない。始めにロンドンから旅をスタートするとやっぱり日本とは違うなと言う実感とともに、外国にいる充実感を感じるが、スコットランドからロンドンだと東京と大差が無くてなんだか損した感じ。
ま、仕事のためにロンドンに立ち寄るのだからしょうがない。ただの観光だったらロンドンなんか来ないよな〜。
到着後、早速なじみの酒屋をチェック。何処も在庫はあまり大差が無い。むしろロンドンの酒屋は割高感があって、今ひとつ取引する気になれない。ワインの種類は確かに多い。また、オールドヴィンテージも多数在庫しているが、シッピングを考えるとどうだろうか。ビジネスとしては全くうまみが無さそうである。やはりワインでおいしい商いをするのは難しそうである。ソサエティーロンドンメンバーズルームへ。ヴォルツのメンバーズルームとは打って変わってモダンなインテリア。両方に言ったことのあるメンバーはその違いを楽しめて、大変楽しいコンセプトだと思う。しかしロンドンメンバーズルームはそのインテリアだけでなく雰囲気が違う。これもまたモダンな印象。言ってみれば、日本のモルトの多いモダンなバーとあまり変わらないかも。
パブは確かにカスクのビターはうまい。しかし、個人的な好みでは、カスクのIPAや80の方が味わいが複雑で高品質な印象を受ける。
どうしても、スコットランド贔屓になってしまうのは旅行してきたばかりだからだろうか?
20 Feb. LONDON
本日は、ビジネスの一日。ウィスキーエクスチェンジを訪問し商談。
それにしても怪しいインド系英国人のオーナー。何でそんなにウィスキーのコレクションに熱心なのか少し不思議。とにかく、受けの良さそうなウィスキーを幾つか見つけて商売的には上出来
。帰りにピムリコ界隈を散歩して良さげなパブへ。IPAを一杯だけ楽しんで、一仕事して帰路へ。最後の一仕事でローズのライムジュース探しへ。フォートナムアンドメイスンであっさり見付け、送料の交渉。思ったより高い送料で交渉決裂。とりあえずサンプルで日本だけ持ち帰ることに。どこかのインポーターでレギュラー商品化すれば一商いできそう。
やはり、大都会ロンドンは、スコットランドとは違いビジネスライク。ついでに、ミルロイにも立ち寄り軽く商談。
次第に仕事モードに嫌がおおにも戻されてゆく…最後がロンドンなのは良いのか、悪いのか。
まとめ!!今回の旅で思ったこと。
情報技術が発達し、効率のいい流通や超高度なデータの情報化に注目が集まる昨今だからこそ人間が大切に思えてならない。結局、美味しいウィスキーも、意心地のいいパブも人間が作り、人間が利用する。
日本に帰ったらこの辺から、もう一度、「豊かな空間」について考えてみたいと思う。
いつもの事だが、英国で教えられた事を煩雑な日本の生活の中で、無くしてしまう事がないように大切にもって帰りたいと思う。
そして日本で今この原稿を作りながら…
「何が高度情報化社会だ!! パソコンなんて大嫌いだ!!
結局、果てしなく人間に優しくない機械を相手に、仕事は増えるばかり…
本当に、世の中は便利で、豊かになっているんだろうか???」 と呟いている川本である。
|
 13 Feb. around 6pm Campbeltown「ザ・バーンサイド」にて。
13 Feb. around 6pm Campbeltown「ザ・バーンサイド」にて。