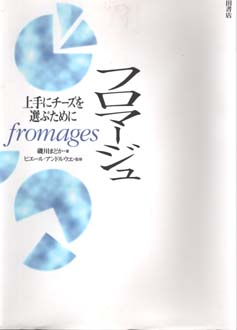マリアージュ……結婚と言う意味ですが、料理と主にワインをはじめとする飲物の組み合わせのことを指して、こう呼んでいます。
どちらが夫で、どちらが妻かは解かりませんが、お互いに協力して我々を楽しませてくれます。ちょっと聞いた感じ、とっつき難いようにも思えますが、実に簡単なことで、「緑茶とようかんは合う」とか「アンパンと牛乳は美味い」などなど、日常生活の中でたくさん見つけられます。自由に、奔放にあなたらしいマリアージュを是非、発見してください。
チーズとワイン
「こちらの、フォアグラの冷静にはソーテルヌがよろしいかと思います。メインの仔牛の胸線肉のプレゼには、Ch Lafit-Rothchild 1982年物、…。」
などと、料理とお酒(又は紅茶、コーヒー)の組み合わせは定番と言うか昔から、よく言われるベスト・コンビネーションがある。
これらの周辺知識をひけらかすとただの「いやみな奴」になってしまうかも知れない。しかし、もっと身近にこの問題をとらえるとこれほど奥が深く、無限の楽しみを与えてくれる知的なグルメ志向は本当に楽しいものである。
とかく日本食というのは、酒を飲みながら食事をするというよりは、酒は酒、料理は料理といった形態をとる。しかし、言わずと知れたフランス料理やイタリア料理を始めとする西洋の食事の形態は、ワインをはじめとする酒と共存する形での食卓が伝統的に存在する。逆にいうならば、食卓に上る代表的な酒をワインとするならば、ワインは食卓無しには成り立たない酒であるとも言える。
ところで、チーズ。こんなに簡単で、手軽で、気軽にグルメな気分を味わえる都合のよい食品は無い。
無論、チーズは「つまみ」となる為に作られた食品ではなく、歴史も古く古代エジプト、メソポタミアの時代にまで遡る。これは、ワイン、ビールなどの古典的醸造酒の歴史と一致する。
さて、ワインにしてチーズにしても、どちらも砂漠の民が作り出した物である。この共通点から、我々水の豊かな国に住む日本人には、今ひとつ理解できない、砂漠の民の水とのかかわりを考えてみなければならない。豊富に水が無い世界では、わずかに天からもたらされる恵みの雨を効率よく蓄え、利用していかねばならないことは容易の想像がつく。この最も有効な手段が、葡萄樹を植えて、その果汁を絞ること、であった。これが後にワインとなる。もうひとつは、雨の少ない環境の中で育ったわずかな草を羊をはじめとする動物に食べさせ、その乳を水分として摂取する、又は、血を同様にする。我々日本人にとってはなじみの無い、食品としての動物の血。しかし、これはヨーロッパなどではごく一般的に料理に用いられることも多く、決して特殊なことではない。かつては、動物の乳を飲む事だって、日本人にとっては奇妙なことだった。(明治維新で、開国するまで日本では母乳以外に人間が口にする乳は無かった。)ワインはどうだろうか。そもそも果物を絞って、ジュースとして口にする習慣は全く日本には無かった。世界的には葡萄は生食用に栽培されることは稀で、ほとんどはワインの原料葡萄である。と言うことは、やはり日本人にとって果物を絞って酒にする行為は、極めて特殊な行為である。
話が少しそれたが、マリアージュに戻そう。経験的に、酒と料理の相性は長い歴史の中で体系的にまとめられてきた。また、チーズとワインは、それらが作られる気候風土、人々の気質などと密接に絡み合って、その組み合わせがなされてきた。そんな、すばらしい(?)マリアージュが生み出された土地を離れ、外国の地に行ったとき、その国でその組み合わせは同じように機能するとは限らない。異なる食文化をもつ国の中では当然、違和感がある。そこで、ある国の食べ物が他の国に行ったときには、それはある一定の時間をかけてその国の食文化の中に、オリジナルのテイストを残しつつなじんでいく。(例えば、日本における洋食、英国のカレーなど。)ここで大変興味深いのは、オリジナルのテイストの残し方である。日本人は比較的この作業に長けていると言われる。洋食は確かに西洋のそれとは異なった物で、オリジナルが無くなってしまっていると思われるかもしれないが、視野を広げてみれば、一方で本場のフレンチや、イタリアンよりもそれらしい料理を日本人が作っていたりする。
つまり、私が思うのは、「日本人の口に合わないから、作り変える。アイデアだけを採用する。」と言うことではないのだと思う。オリジナルを深く観察し、理解した人たちがいたからこそ作り変えの作業がより緻密になったのではないか。ただ、都合の良いように作り変える作業とは一線を画す物だと思う。
冒頭に書いた、古典的マリアージュ。これが良いのか悪いのか、グルメっぽい、気取っている、など様々な印象を受けるだろうが、要は古典的マリアージュの伝える本質的なメッセージを読み取ることが料理との相性を考える上で、最も知的な作業だと思う。
「フランス人だから、そんな、しつこい組み合わせが出来るんだ。日本人にはあわないね。」
などなど、、、よく聞かれる話だが、その背景を理解した上での話ならば、かまわないが組み合わせだけを見ての発言だとしたら、あまりに相手を理解する努力を放棄した勝手な振る舞いである。相互理解が大切なのは、政治やビジネスの世界だけではないのである。逆に、古典的マリアージュのみにとらわれるのもつまらない。もっと自分らしい、新しい発想があった方が間違えなく楽しい。
チーズとワイン。(そして、パン)世界三大発酵食品といわれるこれらの組み合わせ。
勿論、我々日本人の文化ではないがそれを作った人々を理解しつつ、彼ら(彼女ら)の思いつかなかったような素晴らしいマリアージュを生み出すことが、知的なグルメ志向ではないか。
世情が不安定な昨今せめて、食文化の世界は平和にお互いの文化を尊重しながら、いい時代が築けるように願う。
今回はこれにて。それではまたの機会に…