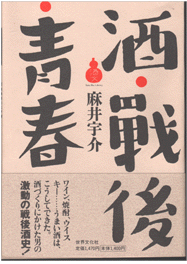世間は、経済再生、構造改革、IT革命…何かが変わろうと大きく動いている気配。カクテルは、お酒は、この十年で何が変わったのか、バブルは酒に何をもたらしたのか?これから何を求められるのか?
いささか主観的ではありますが、自分自身のカクテルやお酒との出会いを振り返りながら、カクテル版「失われた10年」と題してお送りします。
一つお断りしておきますが、私は未成年者でありながら酒を飲んでいましたが、これは基本的に好まれざる行為だと認識しています。未成年者の飲酒は当然、肯定されるべきものではないとも考えております。だからと言って、十代の若者が酒を飲んでいたからと言って、説教しようとは思いません。説教できるような十代、過ごしてませんから!!
飲んだことのあるカクテルと言えば、ジン・フィズ、モスコミュール、カンパリソーダ、そして、ギムレット、マティーニと言ったところ…彼女に何を薦めたらいいのか分らず、結局、そのお店のバーテンダーの方に相談。「何か飲み易くて…」と言ったオーダーをして、出てきたカクテルに彼女は満足。
「バーテンダーって、カクテルっていいな。」と思ったのが、今思えばこの仕事を最初に意識した時かもしれない。しかし、当時の自分が、30歳を過ぎてバー・カウンター越しに逆の立場になっているなんて想像もつかなかった。
ところで、その時のカクテル、多分ピーチ・クーラーか何かだったと思う。いずれにしても、ピーチのリキュールを使った何かだったことは確かで、今となっては、横浜にあったそのBARもなくなってしまい、そのとき一緒だった彼女にあうすべも無く、確かめる余地は無い。
ジン・フィズ、モスコミュール、カンパリソーダ、そして、ギムレット、マティーニ。
これらのカクテルはすべて、スタンダード・カクテルとして広く一般に認められているが、始めの3つのカクテルと、後の2つのカクテルは、ロングドリンク、ショートドリンクなる区分が異なっているのは勿論であるが、それ以前に、もっとそれぞれのカクテルの持つ雰囲気と個性、そして楽しみ方が大きく異なっている。ロング、ショートと言った単純明快な区分ではなく、そのカクテルのもつ雰囲気そのものがカクテルを提供するバーマンにとって最も気になるところである。また、それは飲み手にとってはもっと重要な問題であるに違いない。今回は、特にここ20年程の間に変化が激しかったロングドリンクスについて、日本がかつて無い経済成長を遂げたバブル期を経て人々の趣向の変化とともにどのようにその姿を発展させてきたかを確かめてみたいと思う。
私が思春期を過ごした1980年代は、バブル前夜から絶頂期に差し掛かる頃。街中にクリスタルがあふれていた。トラッドにさりげなく、綺麗なお姉さんがおしゃれな細身のコリンズグラスに入った、赤や、淡い黄緑色の飲み物を飲む姿に一種の憧れを感じていた。背伸びして、自分の住んでいたマンションの1階に出来たカフェ・バーでそれらの飲み物や、バーボンなるものを悪友と飲んでみたりした。初めて口にする、それらのおしゃれな飲み物は、小さい頃にいたずらで飲んだウィスキーのように痛い飲み物ではなかった。口中に広がる柑橘類のさわやかさと、ほのかに甘い口当たりは「酒」を強く感じさせるものではなかった。ただ、ひたすらにおしゃれで、大人だった。バーボンは、かっこいいとは思ったが、なんだか訳がわからなかった。酒を意識させない飲み物が当時の流行であったように思う。前後して、タコハイが発売され、焼酎のイメージも一気に好転したように記憶している。そのとき出来上がった、ドリンクの新しいスタイルは1970年代のアメリカにおける白色革命(・・・つまり、個性的なブラウンスピリッツから何で割っても、バランスを崩さない自由なホワイトスピリッツへの変革。)と同質なものである。
今でもそうかもしれないが、流行はいつでも太平洋を越えてやってくる。自由に、飲み手の趣向に合わせて、アルコールの強さまで調整して楽しめる手軽な飲み物。それらが、当時流行になった、気軽なロングドリンクスであり、チューハイなのだと思う。ただし、前者と、後者には大きな隔たりがあることを指摘しておくべきだろう。前者はハレの日の飲み物で、後者はケの日の飲み物である。サークルの飲み会で、これでもかと言うほど飲まされるのが後者で、デートで飲むのが前者。普通の人が家で飲むのはビールで、ちょっとハイソな人が家で飲むのがカンパリソーダだったりする。余談になるが、それを象徴する興味深い資料がある。当時、一斉を風靡した「ふぞろいの林檎たち」のワンシーン。
中井貴一扮する良雄が、高橋ひとみ扮する夏恵の部屋を始めて訪れた時、彼女はカンパリソーダを手にしている。
さて、白色革命がもたらしたものは何だったのだろうか。気軽に酔える、美味しく飲める、ジュースみたい、おしゃれ。こんなキーワードが浮かんでくる。自分の好みで、過去の習慣にとらわれることなく、自由に飲みたいものを調整できる。しかも飲みやすく、酔っ払いはするが酒を意識させない。
世界有数の経済大国になった日本は自由で、これからバラ色の未来が開けている。アメリカンドリームならぬジャパンドリームがある。そんな、バブル絶頂期にさしかかろうとしていた時代には最高の飲み物であったに違いない。
時代が進むにつれて、無色透明無味無臭のスピリッツから人々の注目は、酒の味を持たない酒へと変化してゆく。そして健康ブームとともに低アルコール飲料へとシフトしている。それは米国で白色革命後、ミドリ、アマレットと言ったリキュールで作る新しいスタンダード・カクテルが誕生した流れを踏襲している。日本におけるその先駆者的存在が、カルーアでありピーチツリーであった。この流れは現在も続いていて、バーで飲まれるカクテルも、酒以外の素材の味や香りを前面に押し出したリキュールを中心にした酒の味を持たない酒へと変化してゆく。そして現在では、カクテルはバーだけではなく、居酒屋で当たり前のように飲まれる時代になった。ハレの飲み物はケの飲み物になった。それは、ハンバーグ、スパゲッティと言ったものがファミリー・レストランを通じて大衆化していったのと酷似している。一方で、大衆化したからこそ、膨大な酒類の情報を整理し人とお酒の出会いの場を創造するバーマンやソムリエの仕事は高度に専門化、複雑化して行くに違いない。
酒は「失われた十年」の間に酒らしい味と雰囲気を失った。「安易に、安く酔うこと」が至上命題になりつつあると言ってもいいかもしれない。一般的な酒場と比べて、高価な部類に入るBAR…
今一度、人々と空間と酒が醸し出す雰囲気を大切にして、「失われた十年」を振り返ってみる必要がある。BARの構造改革も始まったばかりなのである。現在の日本においてBARだけではなく、すべての酒類を提供する飲食店、酒販店、酒類メーカーは始めてその本質的な豊かさを問われている。バブル的ではない、心を豊かにする酒を…
次の時代は、私たちがかつて経験したことの無い「豊かな酔い」の時代であってほしい。そのために今、何が必要なのかを今一度考え直して、酒類業界に携っていきたいと思う。
今回はこれにて。それではまたの機会に…