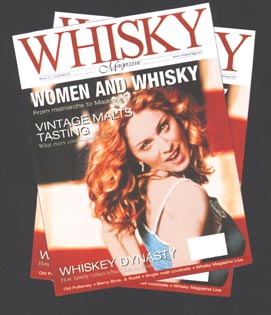近年、特にウィスキー愛好家や、バーテンダーの間で「オールド・ヴィンテージ」がもてはやされています。そもそもウィスキーその他の蒸留酒には、ワインとは異なり、原材料に由来する香りや、味わいは希薄であると言われています。例えば、ワインの世界であれば異なった葡萄品種を用いた時点でそれはまったく異なったものとして認識されます。しかし、スコッチウィスキーの世界では、麦の品種はゴールデンプロミスからトライアンフ、ゴルフとまったく違った品種になっても同じ物として認識されます。つまり、原材料の出来、不出来でヴィンテージが重大な意味を持つワインとは根本的に異なったところにウィスキーのヴィンテージの意味合いは存在するのです。それは、天候、気候、土壌といった神から与えられた条件ではなく、製法全般、時代のニーズへの対応と言った人間の営為に起因するものなのです。「オールド・ヴィンテージ」…この言葉のもつ意味は、飲み手が要求する「本質的な風土性の回帰」の現れだと思います。
高度情報化社会を迎え、以前のように風土性を美化していれば事足りた「ウィスキーらしさ」は今、本質的に風土性の回帰を要求されているのです。
昔と同じように作れば事足りると言った問題ではありません。巨大ビジネスと化したウィスキー業界で、生産にかかわる人々だって、「こだわり」だけでは食べていけません。現地の作り手にだって「都合」はあるのです。
「最近のウィスキーは、美味くなくなった。」そんなことばかり言ってないで、前向きにウィスキーの未来を考えてみるのもウィスキーのプロとして必要なことではないか、と考える今日この頃です。
しかし、ウィスキーその物の歴史を顧みたとき、それが琥珀色の液体としてその「らしさ」を主張するようになるのは、誕生からずいぶんと時間が経過してからのようである。
スコットランドの国民的詩人、ウィスキーにスコットランド人の魂を見出し、賛美してやまなかったロバート・バーンズの時代のウィスキーは、無色透明、強烈なスモーキーフレーバーを持った粗野なスピリッツそのものであった。
少し想像力をたくましくして考えてみてほしい。もし、何かの間違いでバーンズさんが時間と空間を飛び越えて現代に現れたとしよう。彼はきっと世界中でウィスキーなるものが作られていることに驚くだろう。もし、彼と酒を飲む機会に恵まれたなら、とりあえず、日本のウィスキーでも飲ませてみたい気もするが、彼はきっとスコッチを選ぶだろう。このとき、グラスに注がれた琥珀色の液体を見て彼はなんと言うだろうか。彼の知っているウィスキーではないウィスキーを見てなんと答えるであろうか。それが彼の愛したスコットランドで作られた紛れもない、シングル・モルト・スコッチ・ウィスキーであったとしても、それを彼のイメージの中にあるあの粗野な「命」の水に置き換えることは容易なのであろうか。
「ウィスキーの製法は…」と言ったような醸造学的定義によって各々の酒を認識することが一般的に行われるが、我々は上の例のように、その「らしさ」で認識する方が、むしろ人間的で分りやすい。
ウィスキーの歴史を駆け足で眺めると、その歴史はアイルランドに端を発し、酒税法とマーケティング的営為によってゆがめられていく、奇妙な歴史である。やがてヨーロッパからの移民がアメリカ大陸でウィスキーを作り、コフィ・スティルの登場によって原料の多様化をもたらし、連続蒸留により作られたスピリッツは、モルトウィスキーとのブレンドを経てウィスキーになり、フィロキセラによって壊滅的な打撃を受けた葡萄の蒸留酒(ブランディー)の代換え品として英国の上流社会に広まり、世界のブランドとなり、まったく異なった文化をもつ日本にもウィスキーの蒸留技術がもたらされる。大きなその歴史の中で何度となく、熟成の発見、蒸留器(機)の変化、原料麦の品種の変化、原材料その物の多様化、産地の多様化がもたらされてもなお、ウィスキーはウィスキーでありつづける…
飲み手に判然とその個性を知らせる「らしさ」こそがウィスキーの本質を伝えてくれているのではないか。ウィスキー産業が「過去からの伝統を継承する」ことによってではなく、「常に想像しつつ過去を伝統化する」ことによって市場を想像し、世界中に広がっていった。「過去を伝統化する」これは「風土性の美化」と言ってしまってはいささか乱暴であろうか。蒸留所内での自家製麦を前提としたスコッチウィスキーが、技術革新により専門工場での大量製麦が主流となった現代において、その個性を土地と結びつけ、あたかもワインにおける狭義のテロワール的な考えを適用するのはいかがなものか。ウィスキーは技術の革新により時代が進むにつれ土地との結びつきを希薄なものとし、世界市場で受け入れられるに至った。しかし、当初から、「らしさ」だけは飲み手の中に判然と存在し、そのイメージの中で美化された風土性を主張し、商品としての価値を高めてきた。
情報社会の到来とともに、グローバル化が進み、銘酒の評判は考えられない位早く伝わる世の中になった。かつてロマネコンティや、スコッチウィスキーが世界の銘酒になるのに費やした時間に比べたら、想像を絶する速さでその名声は広がってゆく。無論、マーケティング的営為がそうさせる要素は大きい。本質的な意味合いで名声が広がってゆくのとは異なるっているのかもしれない。このような状況下でスコッチウィスキーは今、飲み手から強く「風土性の回復」を要求されているように思う。本質的な意味での「風土性の回帰」…イメージの世界でのみ存在していれば事足りた各ウィスキーの「らしさ」は今、その本質的な部分でも求められている。昨今の、オールド・ヴィンテージへの関心の高さは、その表れの最たるものである。かつてライト化を目指したウィスキーに今、飲み手が求めるものは、逆の方向に向かう事かもしれない。飲み手が求める「らしさ」の果てにはどんなウィスキーが待っているのか。今後が楽しみである。一人のウィスキー愛好家として、現在と未来のウィスキーを批判するだけでなく、慈しみ、暖かく見守ってゆきたいと思う。ティスティング時、賞賛に値するような素晴らしいウィスキーでなかったとしても、何とかいいところを見たい思う。せっかく、世に生まれてきたのだから…
結局、何を言っても「作り手にはかなわない。僕には、作る苦労は分らないから…」
さて、バーマン、ソムリエと言った作り手と飲み手の中間に位置する我々の仕事。関西の銘バーテンダーとして名高い吉田さんの言葉を思い出す。
「ウィスキーには英国の香りを添えて、ワインにはフランスの香りを添えて…」
素晴らしい言葉だと思う。飲み手が求める「らしさ」に花を添える…沢山のお酒に囲まれて仕事をするのは、まるで、お客様とともに毎日世界を旅しているようなものなのかもしれない。
やっぱりいい仕事、選んだかな?
さぁ、今夜はどちらへ?英国、仏国、それとも南の島へでも…「思い込み」って素晴らしい。
今回はこれにて。それではまたの機会に…