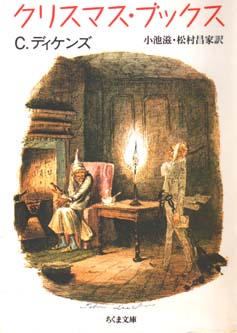この響きにいろいろな思いをめぐらせる方も多いのではないでしょうか。
いろんな人が、様々な思いでその日を過ごす事でしょう。
ところで、クリスマスって何の日だか覚えていらっしゃいますか?皆さん!!
そう、イエス・キリストがお生まれになった日ですよ!!
決して、一年に一度のロマンチックな夜で、口説き、口説かれやすい夜って事ではないんですよ!!
(いや、別に大切な人と過ごすクリスマスなんて、十数年味わっていないサービス業に携わっているものの僻みではありませんからね!!)
さて、それはともかくとして、クリスマスが何故、めでたいのか。私的クリスマスの考察を英国、スコッチ、暖炉などをキーワードにしてまとめて、21世紀最初のクリスマスを祝う原稿にさせていただきたいと思います。
<暖炉>
| OBANのB&B"ROSEBANK"のダイニングに 備えられた重厚な暖炉。 |
英国のパブや一般の家庭では冬になると暖炉が活躍する。
古い物が未だに活躍している英国では、特別な光景ではなく行きつけのパブに暖炉が備えられていることは、贅沢でもなく、珍しいことではなく日常的といってもいいかもしれない。
何度か渡英した折に触れ、その暖炉の良さにことさら安らぎを覚え、何度も足を運ぶようになった。しかも2月の最も寒い季節にだ。現在の店を作るときに、「暖炉がほしい」と本気で考えたが、無論、そんなことはできるわけも無くあっさりとあきらめた。しかしなぜ、暖炉はこうも私の心をとらえてしまったのだろうか。単にそのぼんやりとした暖かさ(決して効率のいい暖房機ではないと言うこと)、そのいかにもアンティークないでたち、酒が美味しそうに映るその淡い火の光、などが欲しかったのだろうか。
それだけのことではない。英国で出会った暖炉たちは皆、人々がその周りに集い、毎日毎日、寡黙に部屋を暖め、人々にぬくもりと安らぎを与えていた。そして、どんな家の暖炉も、大きくても小さくても、古くても新しくても、暖炉たちはそれぞれの職務をよく理解しており、長い生涯を生き生きと全うしていた。ダイニングで活躍する暖炉は一家の成長を幾世代も見守り、パブやクラブで活躍する暖炉は訪れる人々をそっと温かく迎えていた。
そして暖炉にとって、ことさら大切で晴れの舞台が、他でもない、クリスマスだ。サンタクロースを迎えるために相棒の煙突も掃除を済ませてもらわなければならないし、皆が暖かいクリスマスを迎えられるように、ことさら炎を勢いよく燃やさなければならない。クリスマスは、暖炉にとって忙しい季節であるのは寒いからばかりではなさそうである。しかし暖炉は寡黙にその職務に没頭するだけだ。
<ISLAYからやってきたクリスマスの聖霊>
 |
Capital of ISLAY BOWMOREの町の高台に立つ、ラウンド・チャーチ。 |
12月になって何だかんだとバタバタするのはお決まりのことで、これが無くては歳も暮れない。私事で恐縮だが、この忙しい時期に忘れていたことを思い出させる出来事が二つあった。その出来事をお話する前に、少し、私のクリスマスとのかかわりについてお話しなくてはなるまい。
私は、敬虔なクリスチャンというわけではないので、特別クリスマスをお祝いする習慣はない。また、日本で生まれ、この国に育った。多くの人と同じように、クリスマスはサンタクロースがきて、たくさんプレゼントをくれる日、というぐらいの認識しかなかった。それが、特別な意味をもつ日で、果てしなくめでたい日だという認識をもったのはずいぶんと後になってからのことだった。何の縁か、たまたま入学した学校がキリスト教系の学校だったために、クリスマスの前は、さながら学校の至る所がそれ一色だったことを記憶している。勿論、クリスマス礼拝は特別な学校行事の一つだった。
しかし、卒業してしまえば特に熱心なクリスチャンでもなんでもない私にとっては、クリスマス礼拝とか教会なんて遠い過去の事でしかない。
突然アイラの話に飛ぶが、アイラ・モルトの女王と言われるBOWMORE。この著名な蒸留所のあるアイラの首都とも言うべき町の高台にはラウンド・チャーチと言う円筒形の教会がある。何時訪れても鍵がかかっていたことが無く、誰もいなくても自由に中に入れる。信仰心のない私でさえも、そのすんだ空気と静寂に包まれた礼拝堂は、世間の雑事を忘れて無心になれる力を持っている。何度となくアイラを訪れてしまうのはアイラのウィスキーの魅力だけでなく、その教会の魅力もおおいに貢献していそうだ。
こんな話から発展して先日、ある人と賭けをした。「日曜日の朝10時に教会に行く。」教会に行くことを賭けのネタに使うなんて、なんとも不謹慎極まりないとも思うのだが、理由はともかく、礼拝にか来た人を温かく迎えてくれるのが教会だ。なんとも自分勝手ではあるが。結局、諸般の事情により賭けはドローになってしまったが、かつて通っていた学校で毎朝、礼拝があった昔のことを少し思い出した。
数日後、今度はその学校時代のかつての同級生から突然メールが届いた。偶然にも、C&Sのホームページをみて、他の同級生からその噂を聞いたとの事だった。また、レストランガイドなどを見てC&Sの事は以前から知っていたという、驚きのメールだった。
この二つの偶然は、ISLAYから連れて帰ってきた聖霊のいたずらだったのかもしれない。ディケンズの「クリスマス・キャロル」ではないが…!?
「一年の最高の稼ぎ時。
(夢がない。何とも色気のない言い方で恐縮です。しかし、背に腹は代えられません。)いかに多くのカップルに、幸せな一夜を過ごしてもらうかに神経を尖らせ、最高のシチュエーションを作り上げる…これを差し置いて、何がクリスマスですか!!
そう、まさしくクリスマスは最高の稼ぎ時。これを逃してなるものか!!」
こんなことばかりを考えてクリスマスを迎える寂しい飲み屋のマスターに起こった奇妙な偶然。
英国、暖炉、パブ、モルト・ウィスキー、クリスマス…それらが関係付けられた不思議な出来事。
幼い頃に体験した、楽しいクリスマスの夜と荘厳なクリスマスの礼拝、そして、何故か癒されるISLAYのラウンド・チャーチの礼拝堂。
<ハレの一杯、ちょっとその前に…>
 |
Enjoy your Christmas dram....... |
冒頭に触れたように、英国のパブには、多かれ少なかれ暖炉がある。ディケンズの小説にも暖炉が登場するシーン多くがある。人の集まるところには、暖かさと光がある。そして一つの命が誕生した時その場所は一瞬にして明るくなり、暖かくなる。生まれたばかりの命がどんなに無力で、はかなくて、無名で、無力であってもだ。やがてお祝いに訪れる人々が集まり、人の輪ができる。確かに、イエス・キリストの誕生を祝うクリスマスは、世界一大切な誕生日かもしれない。しかし、その特別な日が伝えようとするメッセージの一つは、誰であってもその一人一人の命は尊いもので大切にしなければならないと言う、単純なことかもしれない。(当然すぎることだが、普段の生活で意識することは少ないのではないか。少なくとも私はそうだ。)少し話が大きくなってしまったが、パブでも、バーでも、レストランでも、家庭の中でも、何処でもかまわないけれど、一緒に時間を過ごす人々の幸せと、愛するすべての人々の幸せ、世界中で起こっている不幸な出来事が少しでも良い方向に向かうようにと願う事が一年に一度くらいあってもいいのではないか。それがクリスマスという特別な日のなせる技なのかもしれない。
さて現実の世界に戻って、まずはじめに目の前にいる大切な人々がこの世に生まれてきたことを祝って、そして世界平和を願って、少しだけ、イエス・キリストの誕生を祝って…最高の一杯とごちそうを前にして楽しむとしよう!!!普段は、口にしないすばらしい一杯をクリスマスにかこつけて…
結局、酒飲みはこの一杯が大切なのかも!?ま、何はともあれMerry Christmas!!!!!!!!!!
こんなつまらん原稿を読んでいてくださる貴方に幸あれ!!そして世界中の人々が楽しいクリスマスを迎えられる日がきますように…
もう一度、Merry Christmas!!
いつしか、知らないうちに、「暖炉」のような存在になりたいCASK AND STILL。
ぼんやりと暖かく、淡い光のある場所。年季の入った様子で、毅然と人々の歓談をそっと見守る暖炉のように…
今回はこれにて。それではまたの機会に…